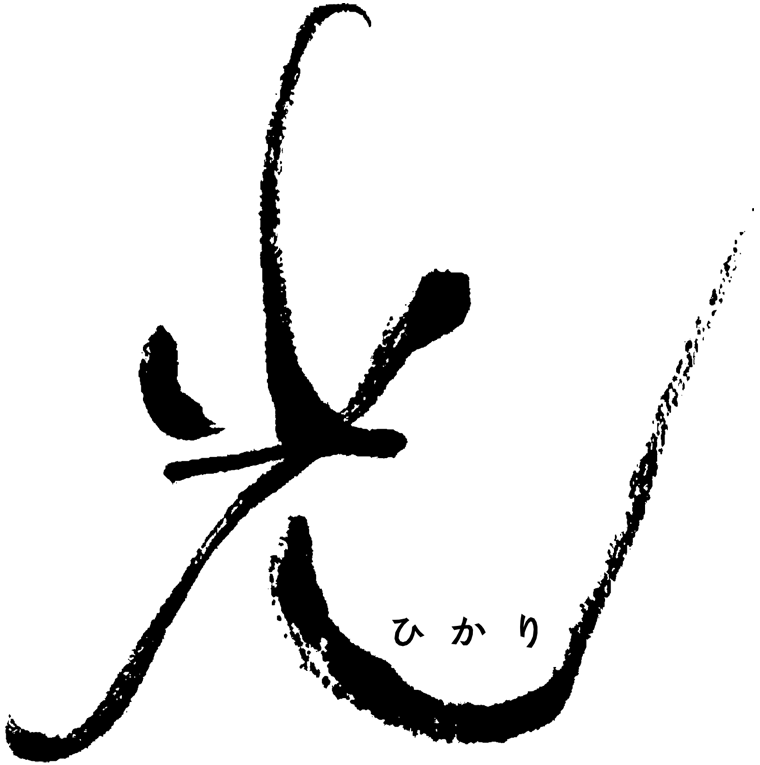
“目を閉じて何も見えず、悲しくて目を開ければ…”こんなフレーズで谷村新司の楽曲『昴』は歌いはじめられる。
よく楽曲を聞きながら瞼を閉じているといろんなシーンが浮かんでくるという人がいる。私は、そんな人をとてもうらやましく思う。残念ながら、私はあまりそういった想像力を持ち合わせていないからだ。夢で鮮明なシーンが現われることもあるのだが、起きているときに目を閉じても、たいてい何も浮かんでは来ない。真っ暗闇が広がっているだけである。まさに『昴』の歌詞と同じだ。なんて想像力が乏しいんだろうと心が折れてしまう。
かつて取材で視覚に障がいのある方々に「夢を見ることがありますか?」と尋ねたことがある。まったくもって失礼な質問だったのだが、みなさん、丁寧に答えてくださった。ある先天的に見えない人は「ぼやーとした形の定かでないイメージみたいなものが浮かんできます」とおっしゃった。「色や形という概念がないからでしょうか」とも。ある途中から視力を失った人は「ときどき目が見えていた頃のリアルな風景が現われます」と。このような話を聞いていると、「見る」とは目でする行為なのか、はたまた脳によるものなのか、分からなくなってくる。しかし、はっきりしていることは、やはり想像力がその底部にしっかりと流れているということではないだろうか。
映画『光』の主人公は、視力を無くしていくカメラマン中森雅哉と視覚障がい者向けの映画の音声ガイドをつくる尾崎美佐子。“珠玉のラブストーリー”と宣伝されているが、テーマはもっと深いところにあるように感じた。それは、“伝えるということはどういうことなのか”、“言葉の可能性と限界はどこにあるのか”ということを私たちに問いかけているように思われた。
美佐子は、担当した映画作品にきめ細かな音声ガイドを挿入していく。しかし、それは監督の意図をまったく把握していないただの行動の説明でしかなかった。そして彼女は、視覚に障がいのあるモニターから「作品の価値を小さくしてしまっている」という指摘を受けてしまう。このモニターの言葉は、私の心にも突き刺さった。
私は、文章を書きながら、いつも「この文章には行間に思いが込められているか」に注意を払ってきた。ただ単に説明に終わっていないかを気にしてきた。理想としているのは“一を語って十を伝える”ということだ。なかなか、それは達成できないでいる。そんな自分の苦悩と同じことがスクリーンで繰り広げられていた。
かつて、視覚障がい者向けの絵画説明イベントをされている方を取材したことがある。美術館に飾られている絵画作品を目の見えない人に解説するというイベントなのだが、その人は「抽象画より具象画の方が解説するのが難しい」とおっしゃっていた。具象画はさまざまなものが具体的に描いてある分、説明に終わってしまうことが多いのだそうだ。説明に終始してしまって、絵画に込められた思いが伝わりにくいという。一方、抽象画は、さまざまな解釈ができ、より本質が伝わりやすいのだそうだ。ただ、それは解説する人の主観であったり偏見などが入ってしまう危険性もはらんでいるという。この主観がだれにでも共有できるような分かりやすいものなら、それはそれで大いに役立つらしい。それには、豊かな想像力が求められている。
映画をつくる人々は、決して視覚や聴覚に刺激を与えるために撮っているのではなく、視覚や聴力を通して“感動を伝える”ためにつくっているのだと思う。
目が見えないからといって感動できることが限られているとは限らない。目が見えない人は、見える人以上に言葉に敏感で、繊細にその意味を解釈しようとしているに違いない。「見えないからこそ、見えることがあるんだよ」という台詞があったが、文章に携わる者として、いつまでも胸に刻んでおかなければ、と思った。
障がいのある人を通して描かれた物語ではあるが、文章に携わる者、いや何かを表現し、伝えることを業にしている人には、ぜひ見ていただきたい作品。“伝えるにはどんなことをすればいいのか”。それを真剣に問いかけてくる102分だった。
Palabra株式会社の「UDcast」が活用されています。





