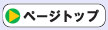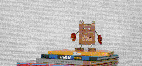< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >

昨年の盆明け8月19日に親父が亡くなった。昨年の節分ころに余命半年と宣告されての結果だったので医者の見立ては正しかったようだ。肝臓がんの末期だった。見つかったときは、もうすでにソフトボール大にまで膨張していた。数年前に心臓病が悪化してペースメーカーを入れていた。加えて動脈硬化もあり、削除手術という選択肢はなかった。お袋のたっての願いで告知しないことにした。だから、親父は自分が肝臓がんだと知らぬまま極楽へと旅立っていった。
最期の半年間は、親子としてあまり話ができなかった。親父本人も病気への焦燥感とか不安感とかで、息子に何を話せばいいのか悩んでいたようだ。こちらも、なかなか正直な態度になれなかった。
今思うと、なぜ、もっと親父の記憶を自分自身の記憶に変換しておかなかったのだろうと後悔している。彼がその人生の中で見てきた風景や匂い、さまざまな音、手触り…。そんな、親父がずっと背負ってきたものを息子が受け取って背負い直す。
これまで、わが国では、そんな営みがずっと繰り返されてきたのだと思う。ぼくは、その営みを少しだけ放棄してしまった。全否定ではないけれど、少しのことが悔やまれてしまうのだ。
このような経験はぼくだけのものではないのかもしれない。日本全国にこの記憶の景勝の断絶は起こっているのではないか。そんな恐怖が少し頭をもたげてきた。ぼく自身もいまは親父となっている。ぼくが背負って生きているこの生きざまを息子たちにきちんと伝えることが、繋げることができるのだろうか。大げさにいうと、その継承如何が日本の未来を左右しているように感じてしまうのだ。
『プリンセス・トヨトミ』は、ぜひ、父親に読んでほしい一冊である。特に息子を持っている父親にである。父の言葉がどれほど大切なものか。それは、父親自身が自覚しなければ、息子には伝わらない。それは、父親自身が自分の父親を信頼していない限り、息子には伝わらない。つまり、受け継いでいかない限り、伝わっていかないのだ。泳ぎつづけていないと死んでしまうマグロに似ているかもしれない。どの代かで、あきらめが生じると、そこですべては絶えてしまうのだ。それをつなぐヨリシロとして父親の言葉は大きく機能する。
クルマのコマーシャルで描かれる子煩悩の父親でなくてもいい。なにかひとつ確固たるものを次の世代に伝えていく。そんな責任感を持っていればいいのだと思う。そんな責任感を持つことがいかにすばらしいか。この本を読めば、きっと、ひとりの父親としての勇気がわいてくるだろう。

幼稚園の年少の頃のことだと記憶している。ぼくは母親におんぶしてもらって、なじみの牛乳屋さんに行く。母親は店の人となにやら世間話に興じている。ぼくが退屈そうにしているのに気がついた母は瓶入りのヨーグルトを買い与える。ぼくは「やった!」と心の中で叫びながらも、退屈そうな表情は崩さない。だって、ここで満足した顔をしていては、これ以上のお駄賃は期待できないからだ。
やがて母親は世間話にきりをつけて、店を出た。そこで、右手にヨーグルトの瓶を持ったぼくがしたことは…。ぼくは指の力をすーっと抜いた。瓶は重力に逆らえず、地面へと吸い寄せられていった。「グシャン」重く乾いた音を立てて、十分に水分を含んだヨーグルトが土の道にはじけた。「あーあ…」母親のまいったなという思いのつまったため息が頭の後ろにくくられた髪の毛越しにぼくの耳に届く。ぼくはそれに答えるように「あー!」と大声で泣きはじめる。仕方なく、母親は踵を返し再び牛乳屋さんに戻って、ぼくにもう一本瓶入りヨーグルトを買い与える。そして、店を出ると、ぼくはすかさず、また指の力を抜いた。「グシャン」今度は母親の声は少し震えている。怒りを噛み殺しているのがわかる。でも、ぼくの泣き声には勝てず、また牛乳屋さんに戻って買い与える。ぼくは、母親を困らせるのが楽しくて、この行為を何度も繰り返した。最後の方で、母親は叫び声をあげていたように憶えている。
なぜ、ぼくは、このシーンを憶えているのだろう。ときどき、地の底からわきあがってくるように、この記憶が意識の中に蘇ってくるのだ。なぜなのだろう。
フロイトに聞けば、父親から母親を取り戻そうとして瓶を落としたに違いない。そして、母親が叫ぶことであなたの精神は浄化された。そう答えるだろうか。ユングに尋ねたら、前世において母親は君の妻だった。君はそのとき、妻よりも弱い立場でその復讐を遂げるために瓶を落としたに違いない、なんて分析されるのだろうか。いずれにしても、この記憶は40年経た今でも、ぼくの心の中に鮮明に刻まれたまま残っているのである。
『記憶のつくり方』を読んで、この記憶以外にさまざまなシーンが蘇ってきた。それはどれも小学生までの頃の記憶だ。長くしまい込んでいた埃だらけの古い箱を開けたときの気分。鼻孔にへばりつくようなカビくさい臭いや煤けた表情を見せる箱の中身…。まるで、人生を虫干ししているような。これを時間旅行と呼ぶのかもしれないな、と妙に納得した。
記憶は、過去のものでない。それは、すでに過ぎ去ったもののことでなく、むしろ過ぎ去らなかったもののことだ。とどまるのが記憶であり、じぶんのうちに確かにとどまって、じぶんの現在の土壌となってきたものは、記憶だ。
記憶という土の中に種子を播いて、季節のなかで手をかけてそだてることができなければ、ことばはなかなか実らない。じぶんの記憶をよく耕すこと。その記憶の庭にそだってゆくものが、人生とよばれるものなのだと思う。
この本のあとがきには、こう記してある。

これまでのイチローのシーズン最高打率は、まだオリックスに在籍していた2000年の3割8分7厘3毛というものである。ちなみに、日本でのシーズン最高打率のタイトルホルダーは、かのランディ・バースの3割8分9厘というもの。阪神優勝の翌年1986年に記録された。海を渡って大リーグでは、1894年にボストン・ビーンイーターズのヒュー・ダフィーが4割4分という記録を残している。1901年以降の記録だとフィラデルフィア・アスレチックスのナップ・ラジョイが4割2分6厘を1901年にマークしているという具合だ。
こうした記録を見ていると、どんな天才バッターでも打席数の60%ほどはアウトになっているということがわかる。つまり半分も成功していないのだ。普通のバッターだと70%以上の失敗率を誇ることになる。逆にいうと30%ちょいの成功率で名選手と呼ばれることになるのである。単純に数字だけを見ていると、なんとなく自分にもできそうな気がしてしまうから不思議だ。
ビジネス書を読んでいると、この数字のマジックと同じ錯覚を感じることがある。“セールス必勝10カ条”とか“ライバルに差をつける20の法則”だとか“なにがなんでも説得5ポイント”なんかの殺し文句が並べられていると、ついつい引き寄せられて、財布のひもを緩めてしまう。そんな経験をされた方も多いことだろう。ま、“これで必ず売れる必勝セールス”なんていうタイトルの本が山と積まれて売れ残っているのを見ると、“そんな人が書いた本って信頼性あるのか?”とついつい疑ってしまいたくなるものだ。
『ラクをしないと成果は出ない』は、ジャーナリストとして活躍する日垣隆氏が、その活動の中で体得したビジネスの心得を「基本」「インプット」「ネットワーク」「撃退」「独立」「継続」「組織」「時間」「アウトプット」「生活技術」という10章に分け、10ずつ合計100の鉄則を掲載したビジネス指南書である。肩の力を抜こうよ、とやさしく語りかけてくれるものもあれば、覚悟しないと痛い目に遭うよ、という刃を突きたてるような厳しい言葉まで、ビジネスの大海原に出航しようとしている人たちに毅然とした態度で対峙している。
特に、これから独立しようとしている人は、事を成す前にぜひ読んでおくといいだろう。もし、この本を読んで、少しでも「こりゃ、マズい」と思う節があったら、今は独立するタイミングではないのかもしれない、と覚悟したほうがいいかもしれない。著者もやんわりとそのことをほのめかしている。いずれにしても、この100カ条のうち、3割を実行できたら、ビジネス界の名選手になれるのかもしれない。とにかく、悩めるビジネスマンに読んでいただきたい。これからの自分の身の振り方の参考になることは間違いない。

ぼくは、雑踏や電車とか、人がいっぱいいるところに行くとついつい人の観察をしてしまうという習癖がある。あの顔はキツネ系だ、とか、友人の○○さんに瓜二つだ、とか…。とにかく他人の顔で遊ばせていただくのだ。ひとりで楽しむこともできるが、何人かでいるときならさらに興が盛り上がる。こんな酷い趣味は最低なのだけれど、どうしてもやめられない。一種の中毒なのかもしれない。ただ、ただ、惜しむらくは、記録として残していないことだろう。これをきちんとまとめて出せばかなり価値があるものになると思っていた。
思っていたら、やはりすでに出ていた。著者はチチ松村氏である。クラゲ、きのこ、桃の収集家として聞こえの高いチチさんである。さすがに、顔を集めてもすらばしい。いや、すばらしい。「太マユゲ」からはじまって、「宇宙人顔」、「地蔵顔」を経由して最後の「トラ鼻」まで、集めに集めた36のヘンな顔たちがどど~んと紹介されている。しかも、いずれの顔も副題がつけられて深みを与えられている。例えば、「カメ目」なら“ハレぼったいマブタのカメ目は一種の天才か?”なんて具合で、ここでは、中島らもさんとダウンタウンのまっちゃんなんかも例にあげられて語られているのである。
そして、この本に奇妙な味を加えているのが、イラストである。とにかく小学生の卒業文集に出てくる似顔絵のようなのだ。これに関しては、対談の中で顔面研究家の南伸坊氏も《この絵はチチさんにしか描けない》と大絶賛している。ある意味、このイラストを見るだけでもこの本は価値を持っていると思う。きっとチチさんのとんでもなく発達した観察力があるからこそ描ける似顔絵なのだろう。彼の場合、観察力は筆力を凌駕するのである。
観察して分析することは、人生を楽しむ上で、とても大切な行為である。そして、その根底には対象への惜しみない愛が必要なのだ。つまり、チチさんは、人が好きなのである。だから、この本を読み終わったときには、とてもほのぼのとした気分に浸れる。表現的には、対象を茶化しているようにも思えるのだが、ところがどっこい彼の人間好きがそこここに散りばめらていて、なんとも温かな雰囲気に包まれているのである。
『顔面採集帳』は、顔面に表れる人格を分類した図鑑である。読めば、人が好きになる図鑑である。対象をとことん好きになるチチさんだからこそつくれた名著である。人が好きで好きでたまらない、人間観察家には、ぜひ、読んでいただきたい。そして、自分で観察した人たちのことを残し、伝えていただきたい。

2~3年前のことだったと記憶している。松岡正剛校長(ぼくは編集学校の師範代なので校長という言葉をつかっている)が、ことあるごとに“これからは、不特定多数ではなく、特定多数なのだ”と繰り返し言っていた。当時は、具体的に何について語られているのかがわからなくて、とにかく呪文のようにアタマの片隅に忍ばせておいた。これは、きっと時限爆弾に違いないと思ったから、忘れないようにだけはしておいたのだ。編集学校での師範代の役目を終えて、しばらくご無沙汰して、今に至っているのだが、最近、例の“不特定多数から特定多数”がムクムクとアタマをもたげてきたのである。
新聞やテレビといった、いわゆるマスメディアの凋落が著しい。広告の売上高でネットに抜かれただの、発行部数が激減しているだの、新聞が新聞社の赤字を伝えているのだから、なんとも皮肉な限りである。でも、確かにマスメディアはその輝きを失ってしまった。新聞を読んでいても、テレビを見ていてもワクワクしたりすることがない。第一、新しい発見がないのである。接触して楽しくないメディアなんて存在する価値はない、とみんなに思われてしまっているのではないだろうか。なぜに、こうもマスメディアは魅力を失ったのか。それを見事に分析したのが『2011年新聞・テレビ消滅』である。
著者の佐々木俊尚氏は、メディアの構造をコンテンツ=中身(番組や記事)、コンテナ=器(新聞紙やテレビ受像機)、コンベヤ=配達システム(新聞販売店や電波)という3C の層(レイヤー)で分析する。マスメディア凋落の原因は、コンテナとコンベヤの変化だというのである。つまり、ネットというコンベヤが誕生し、新しいコンテナが生まれた。それが、グーグルやヤフーなどの検索エンジンである。あるいは、ユーチューブやマイペースなどの配信システムなのだ。今やニュースは新聞紙面で読むものではなく、ウェブ上で読むものになった。動画は、ユーチューブで楽しむものとなった。結局、コンテナを支配したものがメディアを支配するのである。グーグルしかり、ヤフーしかり、ユーチューブしかり。著者は、今アメリカで起こっていることが、3年後には日本で起こると予言する。全国紙の崩壊、そして地デジ化が完了する2011年にはテレビ局が崩壊する、という。
まるで、マスメディアに末期がんで手の施しようがない、と宣告しているような本である。新聞・テレビは、手をこまねいて死を待つしか手立てがないのだろうか。結局、伝えたい相手を想像することもなく情報を垂れ流ししてきたマスメディアに天罰が下ったといえるのかもしれない。存続へのキーワードは、実は“特定多数”の中に秘められているように感じるのだが。そう思っているのは、実はぼくだけなのだろうか?みんなの意見を聞いてみたいものだ。
<